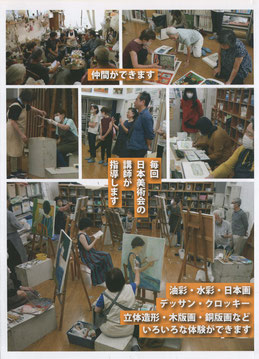第65回展 批評と感想

第65回日本アンデパンダン展実行委員会から「批評と感想」(全56ページ)が発行され、第65回展出品者823名へ6月中旬に発送されました。この冊子は、作品の批評と感想にとどまらず、何人かの方には多様化する最近の美術に関する小論文を執筆いただきました。これらの論文や批評、感想が出品者のみなさまにとって今後の制作の力になれれば幸いです。
日本美術会 会報121号に掲載された理論部による展覧会やアートフォーラムに対する批評及び感想の一部を掲載しました。
展示を拝見して思った事 上野一郎
65回展の「時代の表現 生きる証」には“東日本大震災・福島原発で被災された方々に心を寄せて”とのアッピールが添えられた。そして会場はこの雰囲気に満ちていた。このアッピールがなくても当然、「時代の表現
生きる証」として東北の震災や福島の原発のテーマの作品が多く寄せられただろう。しかしやはりあのアッピールは出すべきなのが組織者としての国民的感情である。なぜこのようなことを書くかといえば、私はあたりまえのことをちゃんと尊重しなければならないと反省するからだ。芸術、創作、発想などには日常的とか常識的な事とは異なった視点があるように思えることもあり、そのため奇をてらったり異常性を強調した制作も登場する。しかし表面的な見え方を超えた指摘や表現は、やはり日常的なことや常識的なことを突き詰めて行ったときに見出される矛盾であると思うからだ。だから、65回展は時代の表現、生きる証の着実な集団的表明となっていた。
ところで『地の種』として諸国の作品が展観された。この国際的広がりは有り難いことで、アンデパンダン展の多様性や交流性を強化した。そこで見られた作品からは、国は違いやや表現も違うが感性的には我々と同じようなものを感じた。世界的に生活状況の基本が同じだと、そこでの表現の模索はこうも共通するものかとおもった。ただこの評の始めに上げたテーマに関しては、ほとんど関心が寄せられていなかったように思えたのが残念であった。絆は欧米では連帯と言う語で表されていたが、その点を各国のキューレンションサポートの方々がもっと訴えてくれていれば、それこそ新しい価値の表現が見えたかも知れないと思った。
日本美術会の趣旨には、「新しい価値の創造」が目的となっている。この点から見ると、アンデパンダン展による活動はもっと意気込まねばならないだろう。すでにそれぞれが努力し忙しく、精一杯の参画をしているとはいえ、「新しい価値の創造」への意欲をあらためて高めなければならないだろう。「時代の表現
生きる証」だけなら、そこに深い浅いの差はあっても、証言(Dokumenta)である。証言にも深く鋭く探求して浮かび上がるものには、新しい価値につながるものが見出されるのであろう。このような創造性が求められる。
会場の展示の方法に異議あり 岡部 昭
平面作品の大半は油絵だが、日本画、水彩、アクリル画、デッサン、版画、きりえと、僅かだが工芸素材の紙や布を使った平面作品があまり区別されることも無く並べられていて、見辛い展示は油画とは違う水彩、版画、デッサンの特性への配慮が欠けているように思いました。
我々を囲む世界を美術として模倣する素材のなかで一番完全なものは油絵とアクリル絵の具だと思う。水彩絵の具の場合その顔料は紙に吸い込まれて質感は殆ど紙の質感なのに対して、油とアクリル絵の具は殆どの色を準備し、描かれたキャンバスには吸い込まれず、その上に層となって顔料と共に硬化して画家が予定した質感までも表現できるからだ。相対的ではあるが、白色絵の具には透明感のジンクホワイトに対して硬質な存在感のあるチタンホワイトがある。赤にもマダー系に対するカドミウム系が、他の色にも夫々10種類以上もあって透明感と存在感が用意されている。デッサンは紙の白色と鉛筆かコンテの線で作られるわけで油絵流に量感とか質感が作れるわけでは無く、その線とその線が作る形に観客が記憶とか想像力を重ねてそれを感じるわけだし、版画の場合、紙の白色と黒インクだけの葛藤で出来るわけだが、真っ黒な色面が存在に見えるか、奥深い真っ暗闇に感じるかは全体の構成から見えてくるわけで、油絵のように、見てすぐそれが世界の何か、理解できるわけではない。隣の油絵を見て、すぐ版画の陰のような淡い墨の色を見ても、汚れにしか見えない。この薄墨色の僅かな濃淡から、現実世界の遠近を感じ、作者の心の揺らぎまで感じるには、自分の感性の感度を十倍も引き上げなければならない。もしこの作品の隣にまた油絵があれば観客はくたびれてしまう。また数は少ないが、紙とか布を組み合わせて世界を作る場合、明らかに工芸の分野だが、利用する布の色は絵の具の色よりは偏った個性があって、ここから作者の意図を探るのは油絵より遥かに違った世界であって、別室にまとめたほうが観客の心に馴染みやすいし、このままだと他者からの批判も共感も遠くに逃げて作者は無視されている思いで、創作の情熱を失うかもしれない。以上の理由で出来うる限りジャンル別に展示することを提案します
日本アンデパンダン展のアイデンティティー 北野 輝
「美術運動」No.139に載っているジャスティン・ジェスティー氏の「日本美術会のアイデンティティー問題」という論文を大変興味深く読んだ。そこには、主として「美術運動」誌を読み込むことによって得られた日本美術会についての見解が示されている。日本美術会は「一つの組織というより、複雑な複合体だ」、そして「一つのアイデンティティーをずっと持てなかったというアイデンティティーを守りぬいたところが興味深い」、と氏は述べている。これは確かに会の本質的な一面を突いているように思われる。私たちはこのような外部からの偏見のない率直な見解に耳を傾けながら、私たち自身による自己検証を進めていくことが必要だろう。
ところで、外目に「アイデンティティーなきアイデンティティー」と見えるのは、日本美術会の運動が、思想・信条、創作方法や表現方法などの違いをこえた美術家たちによって担われてきた(あるいは担われるべきだ)という組織原則に関わっているだろう。思想や創作上の立場を異にする者たちの運動であれば、かつてのように激しい論議も交わされ、様々な主張や対立によって揺れるのは当然である。そこには統一やアイデンティティーなど存在しないかのようにも見えるだろう。しかしこの運動は民主主義的な美術運動を推進するという目的においては一致しており、そのための組織形態としていわば「多元主義的連帯」を図ってきたのだから、これが会の積極的な意味でのアイデンティティーであろう。日本美術会の創立に加わり長年会と歩みを共にされた永井潔さんは、その晩年、あるべき組織形態を「中核規定を持たない多元主義的連帯」にみていた。これはわが会が体現してきた、また課題とすべき組織形態にほかなるまい。
日本アンデパンダン展は、この多元主義的連帯を体現し展開する展覧会であろう。そこには一見無秩序とも見える「何でもあり」の多様な作品たちが並ぶ。第65回展を観ると、3・11による衝撃と刺激は、その多様性を何ほどかふくらませたように感じられる。だがそこに統一があるとすれば、それはヘーゲルが考えたような諸要素が自立性を失って成り立つ「有機的統一」ではなく、諸要素(諸個人、諸作品)が自立した有機的統一、異質なものが共存するだけでなく競合しさえする新しい(?)統一と連帯でなければなるまい。この競合をも含む統一・連帯は、異なるジャンルの展示方法など具体的に解決すべき問題をかかえているが、アンデパンダン展のアイデンティティーとして堅持し、発展させられなければならないものと思われる。
シンポジウムに参加して 菅沼嘉弘
〈3.11とどう向き合うか〉をかかげた今回のシンポジウムは、私にとってとても刺激的だった。「人間にとって芸術とはなにか」この根源的な問いにあらためて気づかせてくれ、これからの意欲につながりそうだと感じたからだ。とはいえこんな大テーマに正解があるはずもなく永遠の問いとなることも分かっている。まずは歴史をふりかえるなど、多角的にじっくり考えていくしかないだろう。その点でシンポジウムでのスライドによる資料提示やレポーターの発言は役にたった。
近代以降の人間の歴史は「戦争」と「テクノロジー」に象徴される。二つの相性の良さはアメリカの歴史が証明済み、戦争やテクノロジーの猛威に異議申し立てできるのは人間の想像力(主として芸術)のみと言われる。美術では戦前の「プロレタリア美術」から戦後の「日本アンデパンダン展」の歴史にその奮闘ぶりがうかがえる。
近年、この想像力の衰退は加速し、生活文化全体を変質するまでになっているとよく言われる。テクノロジーのもたらす仮想空間が、特に子どもや若者たちに、想像力とは似て非なるイリュージョンや妄想を培養、本来の想像力を退化させているのだろう。こんな状況から少しでも脱出するために、まず自分自身でとりあえず次のようなことから初めてみたいと考えた。
・リアルな現実空間へ努めて視線を向ける。想像力とは、事物の本質を感じ取り、生活をきり拓いていく力、つまり私たちの暮らしに《人間らしく生きる》という方向性をもたらしてくれるはずだから。(ヴィゴツキー・メルロ・ポンティ・サルトル…他)
・戦後から今日までの美術の動向など、真摯な気持ちで見直してみる。現代絵画等の発生、展開の意味、その必然性と問題点などの批判的検討(美術手帖7「日本近現代美術史」2005年)。今年の出品作の数々にそのきざしはすでにあふれていることに気がついた。
第65回日本アンデパンダン展を鑑賞して 御笹更生
理論部内外から、より多くの人によって展評を行なうことは大きな意味があると思います。福岡から3月30日、飛行機で会場に出かけ、2時間半ほどで45枚の写真撮影とゆっくりした鑑賞をさせてもらいました。何の系統性もなく任意に記録した作品をプリントして出品目録と照合させ、題名と大きさを確認しながら自宅でじっくり見直しました。
今回の展覧会を質・量のレベルで山脈にたとえるなら、どのような稜線を築けたのか。出品者の一人として、また同時に一般観客の視線も意識しながら思っています。
その一つはインパクト(衝撃)の強さであり、深い感動あるいは共感による充実感・安心感そういったものです。
その一つ目の作品は、山本明良氏の彫刻「out of form」。福島第一原発の事故以来、初めて耳にした専門用語がなじみになってしまった「メルトダウン」を思い出しました。大きな目の形をした素材感むき出しの黒い石に強烈な対比を示すように溶け出したガラス状のものが埋め込まれている。また、靉光の「目のある風景」をも連想しました。
大震災や原発事故への祈りあるいは憤りを秘めた作品が予想通り多数ありました。素朴に「一本松」を描いた作品が数点ありましたし、杉山まさし氏の「ZONE–1」のようにイメージを再構成した横長の大画面もありました。ユニークな空、緑と黄土色の大地なのなか濁流なのか、色彩は、悲劇的な作品によくあるような暗いものではなく、活気のあるもので、電柱が強く遠近を表現して画面中央に向っており、誰もいない広大なイメージです。左手に壊れた車、右側には家屋らしいもの。もっと手前に「核」のマークの標識がたっている。標識は控えめに、車の向こうに小さく描いても効果は十分に出る、主張したいことを全面に出さない手法もあっていいかなと思いながらも、印象深い作品の一つでした。他には、宮本能成氏の「三崎」、山下二美子氏の「氷輪〜風下の地〜」も大作に思い切り表現していました。また、若い女学生を真正面から克明に描いた上原まさのり氏の「ひめゆり学徒部隊に思いを添えて」も、単なる描写を超えて訴えるものがあります。以下、例を挙げると45点すべてを書くことになりますので、総論的に概括します。
アンデパンダン形式が持っている良さは、アマからプロまで誠に多重層的に現代人の心の向きが一望できることです。しかも、日本美術会主催という面から見て、美術家の良心を結集している結果として、戦争に対する批判精神、あるいは大惨事に対する連帯や憤りといったテーマが多く噴出していることは、大きな特色といえます。また、展覧会が質と量において大山脈をつくるという意味で、二面の課題があるように思います。今を生きている者の感性・理性に映るものをテーマとして率直に向き合う「時代性」。
もう一つが「普遍性」のあるテーマ。これは、昔から美学的に取り上げられてきたもので、リズムやハーモニー、空気、空間、存在感、材質感、運動感、神秘感、雄大さ、人間そのもの、風景など時代を問わず人間が驚き・発見しながら追究してきた素朴で身近なテーマ。いずれの表現にも、かにかのバランスが欠けると稚拙になったり、見苦しくなったりします。描写力に長けていてもそれは起るし、技術・経験の少ない人でも、すてきな表現があり得る訳です。この「絵のよさ」、「表現のステキさ」を理解し追求してゆく,質の高さを広げる努力が大切だと思います。そんなことを皆さんで交流できる展覧会であればいいなと思っています。
第65回日本アンデパンダン展の感想 山田 みづえ
東日本大震災、福島原発事故による甚大な物質的被害、精神的な苦痛や東電や国政の不手際に依るいらだち、忍耐を思うと、日本国民そして世界中の人達は心からの痛みを共感する。3月11日から、毎日、あらゆる報道機関を通して、被災状況,今だかってない放射能汚染の拡散、被災者達の苦難に、生々しい恐怖、不安、同情を感じる私は、どの作品からも、この大震災を表現し創作しているのではないかと思い、鑑賞した。多くの作家達が、この震災の被災者に共感し、速やかな復興への祈り、励ましや鎮魂、絆を表現している。各々の作家の心情,思索,主張、表現に共鳴し感動した。
「非審査、自由出品制」としてさまざまなジャンルの作品は、精魂込めて創作され、斬新、自由闊達で、躍動するエネルギーに、溢れている。会期中、毎日、それぞれの作品を鑑賞し、全ての企画に参加出来たら、自分の創作にどんなにか参考になり励みになるかと思った。
国際企画展を、毎年興味深く鑑賞している。現代芸術の国境は、取り払われているものの、やはり、その国独自の特徴、雰囲気、思考、歴史観が、微妙にまた確固と表現されているのが、興味深く、又、色々な新素材が使われ、マチエールが複雑で、それ等が、作家の意図を、巧みに表現しているのに感動した。
陳列の配慮が行き届き、さまざまな企画講演会、シンポジウムが確固として、充実していて、その事は日本アンデパンダン展の凄さだと思う。これからも、世界の「地の種」となって、力強く新しい芽を出し、生い茂って、芸術、社会に貢献し、新しい歴史を切り開いて行くように希望する。
アートフォーラムⅡ シンポジウムに参加して 山中 宇佐夫
国立新美術館の講堂で3月31日の午後1時半から行われたアートフォーラムⅡのシンポジウムに4人のパネラーのひとりとして参加した私は、1964年以降今日にいたるまでの日本アンデパンダン展における作品の展開と時代背景について、参加者の活発な討論のなかで多くのことを学ぶことができた。日本美術会理論部の出席者からも北野耀さんや上野一郎さんの平場からの積極的な発言があり、たいへん心強く思った次第である。
このシンポジウムの中で、特に私の記憶に残ったのは、会も終りに近づいたころのある
年配の方からの質問だった。「私は若いころアンデパンダン展で丸木夫妻の『原爆の図』を見て感動しました。あの作品をどう思いますか。」という内容の問いかけだった。その人の言葉を聞いて同世代の人間である私は「『原爆の図』を見て、私もあなたとまったく同じような感動を覚えました。」と答えた。
『8月6日』と題され、通称『原爆の図』と呼ばれるこの横長の大作は、広島に投下された原子爆弾の一瞬の閃光をあびた人たちの焼けただれた群像と強烈な爆風にたたきのめされた無残な屍の山―まさにこの世の地獄を描き出した空前絶後の作品である。1950年というから、広島に原爆が投下されてから5年の歳月を経て、作品が完成し、ギリシャ風の列柱のならぶ旧東京都美術館で、第3回日本アンデパンダン展にかざられた。当時まだ学生だった私は会場でこれを見たときに、身震いするほどの衝撃を受けた。そしてその“出来ごと”がふりかえって考えてみれば、のちに私が民主的美術運動の一端にくわわるようになった切っかけのひとつになったかも知れない。
『原爆の図』は第一作にひきつづいて連作が発表され、それらのシリーズが巡回展として各国をまわり、評判になって、世界の反核反戦平和運動をはげます貴重な作品として大きな評価を受けるようになったことは良く知られている通りである。丸木位里、俊夫妻が、その後、政治イデオロギー上の見解の相違やその他のゴタゴタで日本美術会から離れてしまったのは残念だが、このシンポジウムでの『原爆の図』をめぐる質疑応答は久しぶりに私を興奮させ、心あたたまる状態に導いてくれた。
「広島原爆の図」について回想するにつけても、3.11福島第一原発爆発事故をめぐる昨今の政府、電力会社の国民をバカにしたウソ八百は何ということか。日本アンデパンダン展よ、ガンバレ!