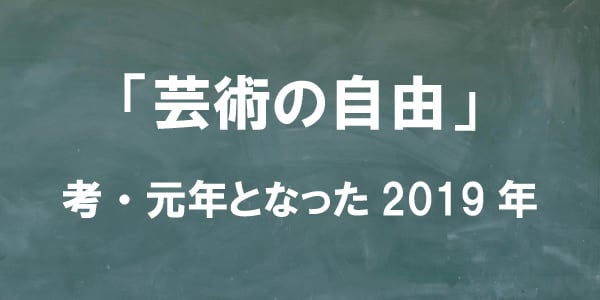
志田陽子(しだようこ)
2019年を振り返ると、日本社会一般が「芸術の自由」というものに関心を持った初めての年だったのではないかと思う。芸術表現がさまざまな「やりにくさ」を抱えてきた事実は最近に始まったことではないのだが、その問題が一般読者向けのメディアでこれほどに取り上げられたことはこれまでなかった。そのきっかけとなったのは、8月3日、「あいちトリエンナーレ2019」の中の一企画である「表現の不自由展・その後」が中止となったことである。
この問題はもともとは、「表現の自由」を持ち出すまでもなく、自治体がいったんは実施するとした事業なのだから企画のとおりに実施する、と言えば足りることだったのではないかと思う。極端な抗議によって支障が出たというならば、一時的な中止は仕方のない判断だったとしても、その後、警察との連携によって可能なかぎり早く再開をするべきだ、という考え方をとるのが普通の発想だったはずである。「表現の自由」を持ち出すまでもない、というのは、これが「表現の自由」とは関係のない地域物産展や公務員試験会場で起きたとしても、同じ判断となるべきだ、という意味である。
しかし「あいちトリエンナーレ2019」に対しては、多数の公人から次々と内容を非難する発言が出され、「表現の自由」によって保護されない内容だ、との誤った見解がメディア上で語られたりしたために、この問題は文字通り「表現の自由」の問題になってしまった。
ここで問題となった展示企画は、中止に追い込まれた後、10月8日から再開され、同月14日に閉幕を迎えた。これに対し文化庁からは、補助金(約7800万円)を交付しないとする決定が表明されている。すでに採択した事業に対し、事業活動の足場となる補助金を交付しないという措置をとることは、制度への信頼を大きく損なうことになるため、美術家の間でも動揺が広がっている。
芸術活動を支援するための財源には限りがあるため、何らかの選別が伴う。このとき、特定の政治関係者の芸術観がその選別を左右することは、慎むべきことと考えられてきた。そうした政治介入からの自由としての「芸術の自由」が日本ではこれほどに確立されていない、ということが可視化されたのが、2019年だった。
「芸術」の領域の表現者は、すでに確立した「芸術」イメージを壊したり超えたりすることを、常に試みている。その格闘を、「これが芸術だ」という誰かのイメージに囲い込むことは、「芸術」を殺してしまうことになる。「芸術」のそうした「青い鳥」としての本質が、社会にはなかなか理解されていない、ということも、今回、かなりはっきり見えてきた。
人それぞれが、自分なりの芸術観を持ち、芸術作品への好き嫌いを語ることは自由である。しかし、公(国や自治体)が文化芸術支援をするというときには、誰かの芸術観によって《芸術の私物化》が起きることを防ぐ必要がある。2019年8月以来、多くの公務担当者がこのことについて理解と見識を欠く発言を行った。公務担当者の発言を抑制する法的ルールは存在しないにしても、筆者が研究者としてこのことを指摘し「それは慎むべきものだった」と述べることは、筆者の「表現の自由」として認められるだろう。
そうしたものは自腹でどうぞ、というのが、昨年1年間に多く聞かれた論調だった。それはそれで、市場で成功できた芸術家が自ら語る自己倫理としては、尊敬に値する見識である。表現は、支援を受けられなくても一般の言論市場に出す「自由」がある。しかし芸術の評価には時間がかかるため、市場での成功だけにゆだねることは難しく、文化芸術支援はこの現実から生み出された実践的な知恵であることを考えると、「自腹でどうぞ」ということは、芸術が育つ可能性を狭めることになる。アンジェイ・ワイダの遺作となった映画『残像』では、支援を受けていた作家が突然に支援を剥奪され、社会の底辺へと落ち込んでいく様子が描かれている。芸術支援が陥ってはならない道を教えてくれる作品である。
多くの人は今のところ、芸術家が公的支援を受けられなくなるという出来事は、社会のごく一部の小さな出来事と思っているだろうと思う。しかし、芸術やポップカルチャーは多くの人の注目を集めるシンボル的な存在である。その扱いは、一般人の「表現」に対する姿勢に、さまざまな形で浸透する。
社会で起きる事象は、すべてが政治的論争となりうる。その中で、「芸術表現は政治的テーマに触れない限りにおいて芸術として是認してもらえる」という了解が日本社会の中で蓄積していくことは、日本のパブリック(一般市民)にとって、深刻なマイナスである。
民主主義は、公共的な事柄について熟議を積み上げていく力を必要とするが、私たちは、その入り口で、悲しみや悔しさといった感性的な部分で触発されることが多い。映画や小説をきっかけにして社会問題を《自分ごと》として理解できた、という経験を持つ人は多いだろう。その意味では、文化芸術と政治を周到に切り離す現在の道行きは、民主主義に必要な基礎体力を奪っていく成り行きになる。
芸術支援と精神的自由は、もともとアンビバレントな関係にある。支援を信頼してそれに乗った後で、「打ち切られたくなかったら自由を手放さなくてはならない」という成り行きになることは、現代国家のあり方として、歪んだコースである。私たちは、そこに陥らないための精神的自由について、考えていく必要がある。2019年は、その問題に人々が気づき、「芸術の自由」に向けた本格的な議論が始まった、記念すべき年となったのではないか。
志田陽子(しだようこ)
武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術法)、博士(法学)。
「表現の自由」、文化的衝突をめぐる憲法問題を研究課題としています。また、映画、音楽、美術など、文化から憲法を考えることをライフワークに講演活動を行っています。



コメントをお書きください