アライ=ヒロユキ 美術・文化社会批評

20 世紀の価値観では検閲や規制は絶対悪で、その否定は絶対善とされた。だが、現代の「表現の自由」をめぐる状況はもっと複雑だ。おそらくこの問題に対し、表現ジャンルでもっとも後衛は美術だろう。
マンガ表現の自由を擁護する活動でも知られるマンガ家の赤松健は(本稿の執筆時点で)参院選からの出馬を予定している。所属は自由民主党だ。
いま文化施設では、政府に批判的、あるいは負の歴史を告発する言論や表現は検閲なり規制をしばしば受けている。新聞メディアへの圧力も強い。その元凶のひとつは自民党だが、赤松の出馬はいかなる思考の倒錯かと訝しむ向きも多いだろう。しかしこれは単純な方便や詐術でなく、そこに「表現の自由」がはらむ複雑な問題がからんでいる。
マンガ表現(アニメなど多種多様の視覚表現も含む)には、「萌え」や「エロ」などジェンダー的観点から問題のある表象が散見される。これに対するフェミニストらの批判、あるいは別種の差別や不適切ゆえの批判に対し、攻撃的応酬も交え断固峻拒する人々を「表現の自由戦士」と呼ぶ。表現の無制限の自由は、差別表現も含むため、むしろ保守勢力に逆用される面もある。日本政府や自治体の広報などの萌え表象の活用は、根底に制度的差別があるゆえだ。そこにある種のおたくが乗っかり、自由を声高に叫ぶ現状がある。

千葉市市政 100 周年ポスターはマンガ家の本宮ひろ志が起用されているが、土建的男性の太腕で千葉市が築かれたような表象イメージで成り立つ。筆者がツイッターで「いかにも本宮ひろ志の世界観だが、老若9人のうち女性が幼女2人だけはあまりにもジェンダー・バランスが不均衡ではないか」と書いたところ炎上した。「フェミタリバン」とも罵られた。これはマンガ家の過誤でなく、千葉市の図版選定と意図が間違っている事例だ。
本宮の作品を探せば、おそらくは使用にふさわしい、男女平等的な趣の図版は幾らでもあるだろう。公的空間の表象には、公共性と使用目的に的確に合致する図像が求められる。しかし、表現の自由戦士はその桎梏が表現の自由を奪うという。最近は、温泉地域おこしの「温泉むすめ」、三重県の海女の萌え化「碧志摩メグ」など、似た事例は多数ある。「真面目な話、日本が自由な表現の最後の砦になりかねないと思ってるんですよね~」とは、赤松支持者のツイートだ。
ここで論点は3つある。表現が無謬無垢でそれ自体無条件で肯定すべきものとの誤解、市民の共有理念でなく各人の利害と嗜好に基づく複数の「表現の自由」、表現の公共空間での使用と私的鑑賞の区別への無理解、だ。
表現の自由が他者、特に持たざるもの、少数者を傷つける可能性は、マンガ表現に限らず、どの表現にもある。もちろん美術表現もだ。美術界でも最近は表現の自由が論じられるが、主要トーンは表現の自由戦士と変わらない。「産業」全体の利害として、美術表現の性善説に基づく自由肯定論が主張されている。マンガ表現だけでは不公平なので、美術表現の「問題視されうる事例」を紹介しよう。
2012 年、国際交流基金はモルディヴで「Breathing Atolls(呼吸する環礁)」と題した日本作家との交流展を開いたが、軍事クーデター直後のため、現地アクティヴィストから「自由のないところに表現もない!」と政治利用を批判された。2013 年、アート・バーゼルでの川俣正がブラジルの低所得者住居を模した《ファヴェーラ・カフェ》は、富裕者による貧困者の表象搾取だとオキュパイされた。
2010年、カオス*ラウンジはSNS「ふたば☆ちゃんねる」のキャラクター「キメこなちゃん」の無断引用、また冒涜的行為が批判を浴びた。2018 年、写真家の荒木経惟によるモデル虐待が明らかになり、海外では広く報道され、抗議行動も起きた。2012 年、森美術館での会田誠展にフェミニストらから抗議があった。
丹羽良徳の《ルーマニアで社会主義者を胴上げする》は共産独裁政権が災禍をもたらした国でのパフォーマンス。岡本光博はかつて日本の植民地、台湾で石燈籠や神社の一部を復元する《橋仔頭神社境内再現プロジェクト》を実施した。飯島浩二の《カンシカメラメカシ(仮題)》は、ドヤ街で知られる大阪・西成の5つの商店街の防犯カメラを造花やおもちゃで装飾し、意識喚起するもの。
上記の大半は筆者が別媒体で既に論じているが、その是々非々はここで論じない。このような事例は美術界でまず議論にならない。仮にあったとしても、一面的に、肯定的議論に陥る傾向がある。被害者あるいは被傷性に留意した、多面的、複合的、公平な議論なり批評は倫理上必要であり、また多種多様な「正義」が叫ばれている世界情勢への応答性でもあるだろう。否定か肯定かの単純な二元論で解決しないことも指摘したい。
一方、あいちトリエンナーレ 2019 の「表現の不自由展・その後」(およびシリーズ展示)が暴力的な表現との指摘もある。日本軍「慰安婦」、戦争/植民地責任、天皇制を美術表現のモチーフや主題に用いることが、日本人の心性なり民族性への侮辱や挑発との主張だ。現に表現の自由戦士系の物書きの言葉に「『表現の不自由展』中止問題と『萌え絵』忌避問題は同じ次元で扱われるべき」なるツイートがある。こうした理解の根底には、善悪、公共性や私的空間、歴史上の真偽など、さまざまな観点での(文化)相対主義がある。
あいちトリエンナーレ 2019 では、社会の分断を克服するため対話が必要と主張された。その対話は被差別者と差別者との間のもので、被傷性や(権)力の不均衡は無視されている。こうした相対主義は結果的に差別などの社会矛盾を温存する。相対主義の対話は「表現の不自由展・その後」への批判とからめて主張されることが多かったが、主張した作家らは当時「Jアート」と左派系から呼ばれ批判された。言論や表現各々は等価でも平等でもない。そこに潜む権力構造を直視する必要がある。いま海外の公共空間の人物像が数多く攻撃、撤去されている。イギリス・ブリストルの奴隷商人、エドワード・コルストンが代表例で、差別制度の加担者が標的とされている。一方、2016年にニューヨークの公園設置の委嘱彫刻にアーロン・ベルが奴隷制批判の意味を込めたところ、強制修正の検閲を受けた。このふたつを同列に見てはいけない。

日本ではリベラル勢においても、ヘイトスピーチにも表現の自由を認める議論が一定の広がりを持つ。被差別者と差別者の言論を同列に遇することは、前者を傷つける。ところが海外では事情は異なる。
ドイツでは刑法 130 条の民衆扇動罪により、差別による憎悪煽動(ヘイトスピーチなど)やホロコースト否認は罪となる。同様の法律はフランスほかヨーロッパ各国にある。ドイツの例は「公共の平穏」を守るためとされるが、それだけではない。ドイツ連邦共和国基本法(憲法)の第一条「人間の尊厳は不可侵である」に依拠するという。
日本の法解釈では、差別や侮蔑の罪の立証には個人あるいは特定の社会集団の法益(利益)が必要とされる。日本国憲法では、尊厳や権利は抽象的な「人間」(人類)でなく飽くまで具体的な個人に帰する。しかしドイツでは人類全体を法益とする考えがある。
ホロコーストは人類全体の問題であり、被害者への賠償だけでなく、社会全体の記憶の継承、歴史問題も肝要となる。そうした歴史問題に関わる法を特に記憶法という。
韓国では軍政府による民衆弾圧の光州事件(1980 年)に対する歴史歪曲を罰する「改正 5・18 民主化運動特別法」(5・18 歪曲処罰法)が 2021 年から施行した。光州事件は現在の韓国民主社会の出発点であり、かけがえのない社会的記憶だからだ。その点で、日本国憲法は現状では不十分、不完全であることに注意したい。
世界の法思想、あるいは「正義」を掲げるアクティヴィズムから窺えるのは、負の歴史と被傷性の記憶に取り組むことが政治的公共性であり、それを礎にしてこそより良い民主主義が実現するという考えだ。そこでは言論も表現も、個人のみに帰する、収斂するのでなく、社会と密接に関係した公共的存在だ。
しかるに日本の表現や言論は個人の権利の発露であり、その無制限の行使や権利を良しとする「思想の自由市場」に依拠する。これは弱肉強食の資本市場の欠点をそのまま受け継ぐもので、新自由主義(ネオリベ)に近しい。
日本の美術界も個人と業界の利害を第一義とし、またネオリベ的価値観と共存状態にある。そこに少数者を、複数性を活かす公共性の思想はうまく根づいていない。ここに問題の根幹がある。
アライ=ヒロユキ
美術・文化社会批評。美術評論家連盟会員/国際美術評論家連盟会員。著作に、『検閲という空気』『天皇アート論』『宇宙戦艦ヤマトと70年代ニッポン』(社会評論社)、『オタ文化からサブカルへ』『ニューイングランド紀行』(繊研新聞社)、『あいちトリエンナーレ「展示中止」事件』(岡本有佳共著、岩波書店)、ほか




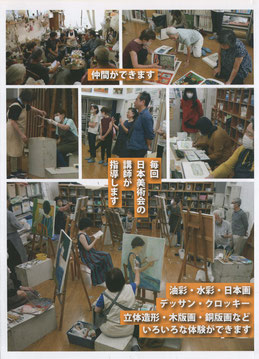
コメントをお書きください
アリア (金曜日, 08 12月 2023 12:38)
>「萌え」や「エロ」などジェンダー的観点から問題のある表象が散見される。
そうおっしゃるからにはあなたは「萌え」「エロ」さらには「ジェンダー的観点」の客観的定義ができるんですね?
個人的感想ではなく、誰が見ても納得する揺るぎない定義が
それができないなら単なる俺様定義による個人的禁忌でしかありません
>これに対するフェミニストらの批判、あるいは別種の差別や不適切ゆえの批判に対し、攻撃的応酬も交え断固峻拒する人々を「表現の自由戦士」と呼ぶ。
単なる批判だけなら問題ないですよ
問題なのは「萌え絵を公共の場所に出すな」と表現の自由を否定する要求するからおかしいと人権問題営業妨害問題になってるんですから
>表現の無制限の自由は、差別表現も含むため、むしろ保守勢力に逆用される面もある。
文章なら差別表現もあるだろうが絵がどうして差別なんですかね?
ただの被害妄想でしょうよ
むしろ絵に対して無茶苦茶な言いがかりやらデマを吹聴をする方が異常ですよ
>筆者がツイッターで「いかにも本宮ひろ志の世界観だが、老若9人のうち女性が幼女2人だけは
>あまりにもジェンダー・バランスが不均衡ではないか」と書いたところ炎上した。
なんで絵一枚にバランスを求めるのですかね
絵一枚で全てが表せると考える方がおかしいでしょう
>本宮の作品を探せば、おそらくは使用にふさわしい、男女平等的な趣の図版は幾らでもあるだろう。
絵からそんな被害妄想をする方がどうかしています
>これはマンガ家の過誤でなく、千葉市の図版選定と意図が間違っている事例だ。
あなたの意図が間違ってるだけ
絵一枚で社会の全てが表れてると考える方がおかしい
>表現が無謬無垢でそれ自体無条件で肯定すべきものとの誤解、
絵一枚で社会を表すとの誤解
絵一枚でバランスを崩すとの誤解
何一つ根拠がない一方的なアライ論法を肯定されるべきという無謬
>いま海外の公共空間の人物像が数多く攻撃、撤去されている。
だからこそ表現の自由が大切なのにねえ・・・
批判は自由だが撤去させるのはおかしいでしょ
>しかしドイツでは人類全体を法益とする考えがある。
ドイツのはちょっとおかしいですよね・・・
人類全体を法益なんて無理がある
「お前には分らんだろうがワシの行動は人類全体のためになるんじゃ」
なんて狂信者の悪役だって法益となってしまう
抽象的すぎていくらでも誤魔化せる
>その点で、日本国憲法は現状では不十分、不完全であることに注意したい。
現日本国憲法が完璧という訳ではないが、いくらでも誤魔化せる「人類全体を法益」なんてのを憲法条文にするよりずっといいですよ
>しかるに日本の表現や言論は個人の権利の発露であり、その無制限の行使や権利を良しとする「思想の自由市場」に依拠する。
権利というのは個々人に帰属するものなんですよ
これがたとえ法人であっても個々人から委託されたものであり、結局は個人の権利を保障するための法人なんです
そうでなければ戦前の「お国のため」
過労死まで働かせる「会社の皆に迷惑をかけてはいけない」
学校のイジメを隠蔽する「あいつがいなければ平穏無事」
とどこが違うのやら
アリア (金曜日, 08 12月 2023 13:13)
>しかるに日本の表現や言論は個人の権利の発露であり、その無制限の行使や権利を良しとする「思想の自由市場」に依拠する。
>これは弱肉強食の資本市場の欠点をそのまま受け継ぐもので、新自由主義(ネオリベ)に近しい。
あんたの発言も社会に数多ある表現の一つでありこうやって自由に発信できてるでしょうに
それと同様に萌え絵を表現してどこが悪いんですか
萌え絵が差別なんて妄想は無しで説明してくださいな
>そこに少数者を、複数性を活かす公共性の思想はうまく根づいていない。
もともと美術芸術なんて儲からない物ですよ
極少数だけがもてはやされて高値がつくだけで
たとえ売れなくても道端で自由に見せびらかすのは自由でしょうよ
少数派を活かすって何のことやら
売れなくても特別扱いしろってか?
テト (金曜日, 15 12月 2023 16:30)
絵なんだから差別文章なんてどこにもある訳がない。
萌え絵の差別性というのは萌えアンチの脳内にしか存在しない。
なのに脳内妄想を元に萌え絵は差別なんて吹聴するんだからオタクが憤るのは当たり前でしょうが。
萌えアンチによる中傷に反論してるだけなのにこの独善的な居直りは救いようがないな。
ジェンダーというのは男らしさ女らしさという客観的根拠のない思い込みのことなんだが、ジェンダーがどうのこうのとうるさい人の方こそが、根拠のない思い込みで中傷してくるのはどういう皮肉というかブーメランなんだろうか。
人類全体法益というのも笑っちゃうしかない。
そもそも国内だけでも利害の対立があり、また理想と理想のぶつかり合いで政治上の対立が絶えることはない。
人が2人いれば理想が違ってて当たり前という前提を筆者は忘れてるのではないか。
理想と理想のぶつかり合いの究極
国が同じ場合ならば内戦
別の国の場合ならば戦争
理想が違うからこそ争いは起きるんだよ。
人類全体法益なんて銘打ったところで、それぞれの理想を背負った連中同士が「自分の考えこそ人類のため。あいつらは社会を破壊する敵」とお互いを叩く世界にしかならないんだよ。
だから「人類全体」なんてお題目で個人の人権を制限してはならない。
人権と人権が衝突した時の調停、つまり公共の福祉でしか個人の人権を制限してはならないんだ。
これ書いてる筆者って、よくもまあ独善的に自分の考えだけを盲信できるもんだ。
通りすがり (日曜日, 07 4月 2024 07:33)
検索してたどり着いた記事。コメント欄には早速記事が批判する対象からの口汚いコメントがついていた。筆者の指摘が理解できないのが、いわゆる「表現の自由戦士」である。
楡 (木曜日, 06 6月 2024 02:15)
筆者の指摘が間違ってるから批判されてるだけなのにアリア・テト両氏のコメントに論理的な反論ができず「口汚い」としかレッテル貼りしかできないのが萌えアンチの限界ですね
萌え絵の差別性なんて萌えアンチの脳内にしか存在しないし誰も証明できてない偏見でしかない
それに人権なんて一人一人の個人にのみ存在するので人類全体法益なんて独りよがりのイデオロギーでしかない
これにちゃんと論理的な反論できますか?
議論の場ではなく自分の論を垂れ流す場でしか発言できないアンチの稚拙な論なんて社会では通用しませんよ
楡 (金曜日, 07 6月 2024 10:21)
それとポスターについてはアライさんが趣旨を理解せず勝手な妄想で叩いたから批判されただけですよね
以下にそのツイッターを抜粋
アライさんは自分がなぜ批判されてるかを論理的に考察する能力が欠けてるのではないか
otakupapa @otakupapa
右隅に「千葉市制100周年記念漫画」とあり、これは表紙で、モチーフはその中の本宮ひろ志氏の漫画です。
この加曾利貝塚の武田宗久氏の話(60年代)に登場してくるのは男性ばかりになってしまうのは、事実であり、これを本宮ひろ志氏の責に帰するのは少々理不尽だと思います
2021-09-19 02:22:43
くだもの選手権 @kudamonokudao
加曽利貝塚を守った方々のストーリーを『千葉市出身の本宮ひろ志先生』が漫画化しそれをポスターに使用しています。
真ん中は中心となった武田宗久さん
右端は当時の市長宮内さん
学生服の2人は武田さんの教え子
特に関係ない子供達は『男2:女2』に配慮していると思いますが
2021-09-19 13:43:59
通りすがり (木曜日, 01 8月 2024 08:51)
気に入らない記事やコメントに理論的な装いをして単に叩いているだけのコメントに、理論的な対応もなにもないですよ。
理解する気なんかないんでしょ?
阿智加 (土曜日, 03 8月 2024 22:25)
もしも萌え絵に差別性が存在するのなら客観的な証拠を提示すればいいのに
それができないから萌えアンチは誤魔化すしかないのですよね
どこが「口汚い」って?
この類の人って自分の嫌いなモノには「差別」だの「口汚い」等々の見当外れのレッテル貼りばかりなんですね
阿智加 (土曜日, 03 8月 2024 22:32)
根拠がなく「差別」なんてレッテル貼りするから皆から問題視されてる、ってことすら通りすがり氏は理解できてないのですか
根拠もなく酷いレッテル貼りするのは中傷という行為なんですよ
”理論的な装い”すらしておらず根拠もなく単に叩いているのはアライ氏であり通りすがり氏の方です
アリア (木曜日, 15 8月 2024 19:49)
ここまできても萌え絵の差別性とやらの証拠が出せないのが答えですよねえ
萌えアンチのやってる事は事実無根のデマ中傷でしかない
marronさん� (土曜日, 12 4月 2025 19:24)
反政府的な芸術作品への検閲や規制は批判してるのに、「萌え」や「エロ」に対しては「ジェンダー的観点から問題のある表象」と言ってしまうのは大いに矛盾していますね。
「萌え」は全く問題ナシですし、「エロ」に関しては既に18禁として規制されています。
にも関わらずまだ「萌え」や「エロ」は「問題のある表象」と言い切るのならその根拠は何でしょうか?
そもそも「萌え絵」は少女漫画から派生した絵柄で当初は確かにオタク男性をターゲットにしたコンテンツでしたが最近は女性や子供にも人気があり、美少女VTuberや萌え系ゲームの「ウマ娘」が男女問わず小学生からも支持を得ています。
もはや若者にとって「萌え絵」は「一般的なアニメ絵の一種」なのです。
なので今後、萌え表現を行政や企業が採用するのは更に増えるでしょうね。
萌え絵を「差別」だとか言ってたらこれからの時代ついていけませんよ。
ちなみにジェンダー平等先進国の台湾は日本以上に公共空間に萌え絵があり、行政も活用していますよ。
marronさん� (土曜日, 12 4月 2025 19:33)
こちらの文春の記事を読んでみたらいかがでしょうか
https://bunshun.jp/articles/-/9502?page=1