今こそ必要な視点。戦後が今や戦前に。
それは旋回する螺旋階段のように、見える風景は同じでも、
同じことの繰り返しでは済まされない。
2年前、ウクライナ・キーウの空にロシアの軍用ヘリコプターが40数機低空で飛来した。テレビニュースで見た光景は、パラシュートがキーウの空を一杯に降下していた。彼らはウクライナの政権を一気に親ロシアの政権に変革する目的だった。ウクライナ全土の空港も同時に攻撃、3日で変革する予定だったが、抵抗に遭いその目論みは頓挫。
プーチンは情報部の甘い情報分析を批判して多数の情報部員をクビにした。そしてウクライナ全土への軍事侵攻を、名目はネオナチズムからウクライナを守るということらしいが、どうも事の成り行きは真逆の感をぬぐえない。この2年間に世界の経済、政治など、広範囲に深刻な影響を与えている。犠牲になった軍・民間人は数十万人(死傷者)を超え、ウクライナからの難民は数百万を超えている(日本にも2500 以上来ている)。
昨年、パレスチナのハマスによって引き起こされたテロ行為、イスラエルの市民への殺戮と人質の行為は、その後のイスラエル軍のガザへの侵攻となり最悪のジェノサイドに拡大し、犠牲者は数万人、子供の犠牲が多いと報道されている。 負の連鎖が終わらない。その負の歴史を語るには本誌のキャパでは足りない。だからと言って美術の雑誌がそこから目をそらすことはできない。 日本美術会が、第二次世界大戦の悲惨な経験のもとに1947
年に創立された経過の上に、今なお在るのだから。戦争と美術史の関係を再び問う事は、戦後から「戦前」と評される今日、あらゆる価値が動揺し、混乱した敗戦直後の美術史の語り部として、本誌の役割を自覚している。勿論、今を知るには、過去に学ぶという真理の故からである。
(編集・K)



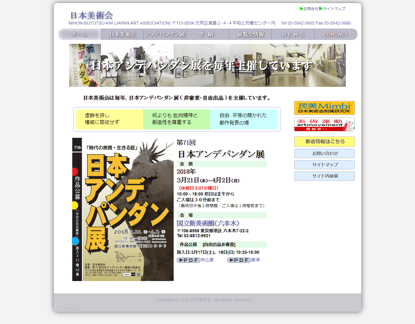
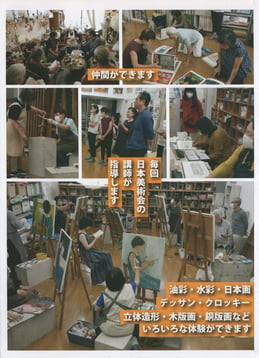
コメントをお書きください