北原 恵 きたはらめぐみ

(1)はじめに:広がる関心
最近、女性画家と戦争について関心を持つ人が増えてきて、長年細々と研究してきた身としては嬉しい限りである。
その広がりの理由として、NHK のテレビ番組で女流美術家奉公隊や長谷川春子らが取り上げられたことも大きい。2022年夏、一般視聴者に向けて放映されたETV 特集「女たちの戦争画」は反響を呼び、放送時間を拡大して「春子と節子 “女流”画家を超えて」(2023 年春)が制作され、また、人気番組「日曜美術館」の枠でも取り上げられた。
テレビを見て、実家に残る関係資料を番組担当者に知らせた人もおり、私自身も、番組の感想を研究者仲間と話し合うなかで、お互いに知らなかった資料の情報交換につながった。※1
このように関心が広がることによって、絵画や資料は意味を持ち、あらたな人々によって見い出されてゆく。
ごく最近にも、女流美術家奉公隊で活躍した中谷ミユキが、戦争末期の「勝利の少年兵」展(1944 年)に出品した油彩画や、長谷川春子の大きな油彩画(1937 年)が、ヤフー・オークションに登場していた【図版1】。残念ながら二作品とも落札し損ねたのだが、絵画の所在が明らかになったのは、研究者として有難い。これらの実作品だけでなく、女流美術家奉公隊が自分たちの活動を知らせる『会報』や主催した展覧会の目録など、一級の一次資料が、次々と見つかっているのである。その活動期間は、1943 年の結成から敗戦までわずか3 年あまりだが、奉公隊について未解明のことは多い。
いったい、どんな資料が発見され、なぜ重要なのか? そこから何がわかるのか? 本稿では、女流美術家奉公隊の『会報』(第1号&第6号)、1943 年の「陸軍記念日 女流美術家奉公隊献納展目録」、「女流美術家奉公隊隊員名簿」などを紹介しながら、最新の研究状況を報告する。
※1 本稿は2023 年12 月に開催した小さな研究会での発表をもとにしており、参加者に感謝したい。
(2)女性画家と戦争をめぐる先行研究
資料の紹介に入る前に、日本の美術史研究において戦争と女性に関心を持たれるようになった状況について簡単に触れておく。それは30 年前から始まった。
1990 年代に入っても美術界では「戦争画」はタブー視されていたが、1994 年に美術史学会が「戦争と美術」をテーマに全国大会を開催した頃から、状況は変わり始めた。と同時に、社会学や文学、歴史学など他領域と比べて著しく導入の遅れたジェンダーの視点も、女性の研究者たちによって提唱され始める。若桑みどり(イタリア美術史)は、第二次世界大戦中、日本人女性がどのように戦争に動員されたかを、雑誌『主婦之友』の表紙を通して分析し、千野香織(日本中世美術史)は、さらにポストコロニアルや国家/ 権力の優劣の視点からも研究を深め、ジェンダー研究を切り拓いていった。※2
若桑や千野らと一緒に私も1995 年の結成に参加したイメージ&ジェンダー研究会は、ジェンダーの視点を視覚文化の研究に持ち込もうとする意欲的な研究者や学芸員、アーティストらが集まり、「戦争」はその中心的テーマのひとつとなった。そして、千野や若桑に学んだ吉良智子は、戦争末期に結成された女流美術家奉公隊の≪大東亜皇国婦女皆働之図≫(1944 年、以下≪皆働之図≫)を中心に、このテーマに長年取り組んできた。※3
戦時下の女性画家の活動や作品については、1990 年代以降、若桑に典型的なように、表象分析が研究手法の中心だったが、それぞれの個別作家の研究や地域研究も少しずつ進展している。2001 年に小勝禮子が企画した栃木県立美術館の「奔る女たち 女性画家の戦中・戦後1930-1950 年代」展は、個々の女性画家だけでなく、制度やネットワークの一端を明らかにし、研究の先鞭をつけた。私は女流美術家奉公隊のリーダーだった長谷川春子や、日本画部を率いた谷口富美枝に興味を持ち、彼女たちの生涯を明らかにするとともに、美術で用いられる用語の銃後/ 前線の境界について検証してきた。※4
また、植民地の絵画についても実証的な研究が、若い世代によって着実に進められ、長谷川春子については、戦前・戦後に書かれたエッセイなどの作品集も続けて出版された。※5
※2 若桑みどり『戦争がつくる女性像 : 第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』筑摩書房、1995 年:千野香織「希望を身体化する―韓国のミュージアムに見る植民地の記憶と現代美術」『神奈川大学評論』39、2001 年.(千野香織著作集編集委員会編『千野香織著作集』ブリュッケ出版、2010 年に再録)
※3 吉良智子『女性画家たちと戦争』平凡社、2023 年:同『女性画家たちの戦争』平凡社新書、2022 年:同『戦争と女性画家』ブリュッケ、2013 年。
※4 北原恵『アジアの女性身体はいかに描かれたか』:北原恵編『科研報告書 特集: 谷口富美枝研究 ―論文・資料集』2018 年:北原恵「「戦争画」概念再考―「空襲」は銃後の図像か」『東アジアの中の戦後日本』(坪井秀人編)臨川書店、2018 年:北原恵「戦時下を生きた女性画家と“越境” ――長谷川春子・谷口富美枝・新井光子」『ジェンダー研究』お茶の水女子大学ジェンダー研究所、no.25, 2022 年(Web 公開)
※5 長谷川春子『踊る女と八重桃の花』共和国、2022 年:同『源氏手帖』同、2023 年。

(3)長谷川春子と女流美術家奉公隊
1)長谷川春子
では、女流美術家奉公隊とはどんなグループで、長谷川春子は誰なのか?
昨年の『美術運動』で、敗戦直後、日本美術会が作成したとされる「戦犯リスト」に関して報告したのだが※6、私がそもそも「戦犯リスト」に関心を持ったのも、「反省を求める者」の団体のなかに女流美術家奉公隊が含まれ、「自粛を求める者」として挙げられた14 名のなかに、同隊隊長の長谷川春子の名前があったからである。
長谷川春子(1895-1967)は、1930 年代から40 年代にかけて満州、蒙古、中国南部、フランス領インドシナなどの戦地を訪れ、日本軍の「活躍」を洒脱な文章と絵画で伝えると同時に、関東の女性美術家たちを繋ぐネットワークの中心で活躍した女性画家である。
1895 年、東京で弁護士を父に7 人兄弟の末っ子として生まれた長谷川春子は、日本画を鏑木清方に、油彩画を梅原龍三郎に師事し、恵まれた環境のなかで育った。姉・長谷川時雨が主宰する雑誌『女人芸術』(1928-32)に挿絵や文章を意欲的に書き、1929 年フランスに渡ると藤田嗣治と交流して個展も開催。帰国時にシベリア鉄道で大陸を一人で横断し、建国間近の満洲を見て感動した彼女は、翌1932 年、さっそく日本軍の協力を得て大連・新京・奉天・ハルピン・内蒙古などを廻った。それは戦争と関わった画家として早い行動だった。
1920 年代から30 年にかけて日本では、美術の大衆化が大いに進んだ時期である。長谷川春子や女性画家は、美術界の男性優位と不平等に直面しながらも、女性画家のグループを結成し、お互いを支え合った。日中戦争が始まると、長谷川はすぐに新聞社と雑誌の特別通信員として中国北部や蒙古に、拳銃を肩にかけてズボン姿で向かう(このときの従軍記録は『北支蒙彊戦線』1939 年)。1938 年、大日本陸軍従軍画家協会が結成されるとその発起人にただ一人の女性として名を連ね、その第一回展に戦争画を出品した。休む間もなく彼女は、1939 年には陸軍省の派遣で中国南部や海南島や、フランスの支配下にあったインドシナを廻り(『南の処女地』1940 年)【図版2】、これらの体験を雑誌や聖戦美術展や陸軍美術展などで次々と発表した。
※6 北原恵「日本美術会「戦犯リスト」をめぐる、いくつかの疑問」『美術運動』(日本美術会機関誌)No.150, 2023 年3 月。拙稿では、日本美術会は「戦犯リスト」を公式発表していないにもかかわらず、美術史ではリスト公表が定説とされていることを疑問視、検証した。
2)女流美術家奉公隊
「女流美術家奉公隊」は、長谷川春子が、戦争末期の1943年2月に陸軍報道部の指導の下で、洋画を中心に、日本画、彫刻、工芸に携わる女性画家たち約50 名を集めて結成した団体である。彼女たちは、母親たちに息子を兵士に差し出すことを促す「戦ふ少年兵」展や「勝利の少年兵」展を日本全国で開催し、銃後の戦争協力を推し進めた。
そして、奉公隊が陸軍省の依頼を受けて共同制作したのが、戦地の男性に代わって働く銃後の女性労働をテーマにした大作≪大東亜皇国婦女皆働之図≫(1944 年、3 部作)である【図版3】。2015 年、私は吉良や小勝らの研究者を誘って福岡の筥崎宮に行き、≪皆働之図≫(春夏の部)を調査したことがある。何十年もお蔵入りになっていた横3 メートルの大作は、保存状態がよく、その明るい色彩に皆で驚いたことをよく覚えている。だが女流美術家奉公隊については、まだまだわからないことが多い。たとえば、≪皆働之図≫は「春夏の部」「秋冬の部」と「和画の部」を合わせた三部作だと言われていたが、「和画の部」は所在不明であり、実際に制作されたかどうかすらわからなかった。それが、奉公隊の『会報』6 号の発見によって、確かに描かれていたことが判明したのである。

「大東亜戦皇国婦女皆働之図作成」― 昭和十九年一月五日準記録画の目的を以て油彩三百号二枚を四十四名にて合作、別に和画一枚執筆者十一名にて共に三部作として陸軍美術展に特陳列、後陸軍省へ太洋文化協会林仙之大将、当隊委員長の共同の名に於て献納す」(『会報』6 号、3 頁)
「準記録画の目的」とあるのは、女性画家は排除され、内地出身の日本人男性のみが描くことを許された作戦記録画を意識してのことだろう。
女流美術家奉公隊については、新聞・雑誌、展覧会関係などの文字資料のほか、吉良智子による元隊員への貴重な聞き取りや、≪皆働図≫の調査が、主要な基礎資料としてある。なかでも組織の解明に重要なのが、「女流美術家奉公隊隊員名簿」(1944 年版)である。この名簿には、隊員の氏名、日本画・洋画・彫刻などの制作メディアの別や、住所まで記されており※7、数は少ないが朝鮮や中国の地名も見られる※8。
奉公隊については、これまでも新聞雑誌などの文献資料に基づいて、研究者たちはその歴史を把握していたが、奉公隊のニュースレターである『会報』が、最近相次いで発見されたことによって、彼女たちの具体的な活動の詳細や、自分たち自身が活動をどのように位置づけていたのかをさらに正確に読み取ることができるようになった。今、見つかっているのは、1号(1943 年5 月発行)と、おそらく最終号であろう6 号(1945 年5 月)の2 号だけである。創刊号からは、創立時の陸軍美術協会側との共同作業や「熱気」が、具体的な日付と人名のもとに浮かび上がってくる。具体的に見ていこう。
※7 名簿には、役員7 名(委員長:長谷川春子、常任委員:谷口仙花・中谷ミユキ・藤川榮子・三岸節子、委員:甲斐仁代・桂ユキ子)を含む正隊員62 名の名前が記載されている(油画部48 名、日本画部8 名、彫刻部2 名、工芸部4 名)。さらに、青年隊48 名を合わせて110 名が参加していた。
※8 本稿を執筆する過程で、名簿に記載された「斎藤雪枝」(住所は朝鮮・慶州)について再調査したところ、1948
年まで斎藤雪枝の名前を使っていた洋画家の高須靱子だとわかった。高須靱子(1909-1984、元女子美術大学教授)については稿をあらためたい。
(4)『会報』1 号と6 号
1)『会報』1 号
1943 年5 月の『会報』1号は、活字縦書き6 頁のミニコミである。桂ユキ子が描いた題字カットの下には、東京・麹町の陸軍美術協会内が住所として記されている【図版4】。
巻頭には中谷ミユキの「創立より結成まで」が掲載され、長谷川春子の指導のもとで、中谷が実質的に事務局の中心にいたことがわかる。2 月5 日、陸軍美術協会で行った創立委員会には、協会側から住喜代志と鈴木清が、奉公隊側から長谷川春子、三岸節子、藤川榮子、甲斐仁代、谷口仙花、桂ユキ子、中谷ミユキの7 名が出席した(この7 名が奉公隊の役員を担う)。その後、創立委員会から2 月25 日の結成式までの20 日間、急ピッチで準備が進んだ。
陸軍報道部が送った結成式の祝辞では、女性画家の「婦人ラシイ繊細ナ気持ト親切ナ気分トデ描レタ一輪ノ花ノ絵」が傷ついた兵士たちを癒すと語り、戦争画の制作にはハナから期待していなかったことが明らかである。また、芸術には国境がないので、「大東亜ノ女流美術家ニ呼ビ掛ケ之ヲ主導シテ」と述べているように、当初は、日本内地だけでなく、植民地や占領地にいる女性画家を取り込もうとしていた可能性もある。結成後、最初の大きな活動として、奉公隊は、陸軍記念日の3 月10 日から20 日まで、献納画展を銀座・日本楽器店で開催した。120 名余による献納画展に、台湾の有名女性画家の陳進が≪少女≫を出品していたことがあらたに分かり、大変興味深い。陳進だけでなく、朝鮮半島にいた斎藤雪枝、山田キミ(夫は山田新一)の名前も、「陸軍記念日 女流美術家奉公隊献納展目録」と『会報』(1 号)の「献納作品目録」には記されている※9。
そして、会場のすぐそばの三越で開催していた陸軍美術展覧会に、奉公隊は連日駆けつけて奉仕し、前線将兵への絵葉書に2万通の慰問文を集めた。この慰問文を募集する様子は、当時の新聞にも掲載され、奉公隊の展覧会自体よりも重視されたことがわかる【図版5】。
※9 陳進と山田キミは、女流美術家奉公隊のその後の展覧会に参加した形跡はなく、隊員名簿にも名前はない。

2)『会報』6 号
新しく発見された資料のなかでも特に重要なのは、1945 年5月付の女流美術家奉公隊の『会報』第6号である。「明朗敢闘将兵慰問号」の副題を持つ同号は、全部で4頁。創刊号よりも薄くなっているが、奉公隊のそれまでの活動や巡回展の歩みがまとめられ、最新の役員構成も掲載されており、初めて知る情報が多い。
1 頁目の巻頭には、長谷川春子による文章「我等の勝算」が載り、いずれは枯渇する敵のガソリンよりも、枯渇しない日本の精神力によって、思想戦と実戦を勝とうと檄を飛ばしている。さらに、「女流美術家奉公隊心得」では、「日本の男と同じお腹から生れた我等」である女性画家は、仕事で魂と真心を現すことを信条とせよ、と説く。
3 頁目には、結成式から1945 年2 月末現在までの足跡を記録した「奉公隊の略歴」が載っている。1 頁目の「勝算」の強気とは裏腹に、自分たちの活動の終わりを見越しての総括のようにも見えてくる。公的記録として残したかったのだろう。 女流美術家奉公隊は、1945 年5 月22 日から東京駅で「明朗敢闘絵巻展」を開催し、駅の1・2等待合室に長谷川春子の≪神風鉢巻≫を飾り、駅前の街頭に隊員らの絵画を並べた。『読売新聞』にはこの展示の写真が掲載されている【図版6】。『会報』には、3 月10 日の東京大空襲に際して、隊員の岡田節子と小田晴子が、奉公隊の事務所から「我々の分身のような血の通ふ大切な四枚の百二十号の連作を残雪の上へ」持ち出して救った奮闘記が掲載されており、『読売新聞』の写真が、まさにこの四連作だとわかった※10。
『会報』6 号で初めて知ったことのなかに、陸軍恤兵部に献納したという『皇軍慰問帖』の存在がある。色刷り菊版50 頁から成る『皇軍慰問帖』は、表紙には仲田菊代の蘭の花の絵が、口絵には、≪皇国婦女皆働之図≫(春秋の部、原色)に続いて隊員の作品が、写真は「合作和画等」が掲載されたとある。「合作和画」は≪皆働之図≫三部作の日本画のことだろう。中身は、画文「決戦女性十二か月」や、合作「愛國いろはかるた」、隊員の自画像・写真などから構成され、隊員の概ね90%が執筆したという。『皇軍慰問帖』は、献納以外にも隊員用として2,3 部存在するようなので、今後の発見が待たれる重要な資料である。
※10 「明朗敢闘」の120 号 4 枚は、桂ユキ子≪帝都郊外≫、寺田榮枝≪B29 来るとも≫、櫻井悦≪深夜の鉄鋼増産≫、小田晴子・田中田鶴子・岡田節子≪学徒飛行機工場挺身≫合作である。
(5)今後の課題と問題点
最近発見された『会報』は、創立期を記録した1 号と、活動の総括をした6 号だけであるので、2 号から5 号が発見されれば、1943 年後半から45 年初めまでの足跡をより詳細に知ることができるだろう。従来、制作されたかどうかもわからなかった≪皇国婦女皆働之図≫の「日本画の部」が11 名によって完成していたことや、未発見ではあるが『皇軍慰問帖』という重要な作品資料が存在すること、1945 年5 月末に東京駅で開催した「明朗敢闘絵巻」展に、どんな作品を展示したかが明らかになった。
戦争末期にはメンバーの多くは疎開していたはずだが、なぜ彼女たちはそれほどまでして活動を続けたのだろうか? そこには戦争終盤になって初めて公の大義を与えられた女性画家たちの、表現する「喜び」と「自負」があったはずである。≪皆働之図≫(春夏)には、隊旗を掲げて誇らしげに行進する女流美術家奉公隊の姿が描き込まれている。だが、「自己表現」の側面だけにフォーカスすると、見落とすことがあるのではないか。戦争と女性画家をめぐる研究について、気がかりな点や今後の課題を最後に述べたい。
第一に私が気になっているのは、女流美術家奉公隊と長谷川春子に関する最近のテレビ番組において、長谷川の戦時中の満洲・中国、ベトナムなどでの従軍や戦地体験がほとんど触れられていないことである。他の民族をどのように眼差していたのか。植民地や「内地」の外での具体的な活動の足跡を明らかにし、民族や階級の視点から分析する必要がある。
長谷川は、足かけ3 年遊学したフランスやヨーロッパの文化に対して憧れとコンプレックスをない混ぜにした感情を抱く一方、満洲を「日本の弟や子ども」と見做し、南越(ベトナム)を「眠れる処女地」の未開地だと捉え、朝鮮をプリミティブだと蔑視していた。アジアの諸地域に対して、日本や自分自身を庇護者たる上位に位置づける長谷川にとっては、日本の様々な地域から男たちが集まる戦場は、「平等」を感じられる空間ですらあったと吐露している。加えて長谷川の戦後の活動を「源氏物語絵巻」の制作のみに収斂させるのではなく、高度経済成長期にメディアでもてはやされた彼女の「毒舌」の思想性を解明することが重要だ。
第二に、戦時下と占領期を連続させて、貫戦期における戦争と女性画家の関係をとらえる必要がある。敗戦直後、女流美術家奉公隊のメンバーはすぐに活動を開始したが、「平和を願っていた女性画家」と、「好戦的だった長谷川春子」の二項対立の図式から当該時期の彼女たちの活動をとらえるのではなく、戦争と切り離すことによって形成された戦後の「前衛」概念の創出過程や、平和の象徴を担わされてきた「女性性」の役割を踏まえた理論化が必要だ。
第三に、有名な一部の女性画家だけでなく、その他の貫戦期の女性画家に関する実証的研究の不足である。中上流階級以上の出身者が多い女性画家にとって、「日本人女性」のなかに存在した差異や差別はいかなるものだったのか。台湾・朝鮮・中国も含めた「日本人女性」の活動を明らかにすること。
女流美術家奉公隊の結成のちょうど1 年前、1942 年1 月に、長谷川春子は海軍の支援を受けて「女流画家報国会」という団体を結成していた。だが、奉公隊と同規模かそれ以上だったと思われる報国会がなぜ途絶したのか。女性画家と海軍/陸軍との具体的な繋がりについても調査が必要だ。
軍部が女流美術家奉公隊に期待した主要な任務は、「戦ふ少年兵」や「勝利の少年兵」展の全国巡回などによって、少年兵をリクルートし、息子を国に差し出すように母親を啓蒙することだった。それは帝国主義日本において、どのような意味を持ったのか? ロシアとウクライナ戦争に喩えて言えば、ロシアの女性美術家団体が若者を戦場に送り出す活動をしているにも等しい。日々、戦争報道を目にすると、私は戦時中の女流美術家奉公隊の活動と帝国のフェニミズムの加害性について考えずにはいられないのである。
「戦争中は多かれ少なかれ皆戦争に協力したのだから」という声が研究者のなかでも聞かれるが、長谷川春子は、戦中も戦後も戦争協力を反省する言葉を一度も残さなかった。1920年代から30 年代にかけて、女性としては珍しく渡仏・遊学して戦地を訪れた「奔放さ」と女性画家たちをサポートしたフェミニストの長谷川の欲望は、私自身のなかにも潜んでいるかもしれない。それゆえ、決して他人ごとではないのである。
北原 恵 きたはらめぐみ
大阪大学元教員/美術史・表象文化論・ジェンダー論著作に『アート・アクティヴィズム』、
『攪乱分子@ 境界』、『アジアの女性身体はいかに描かれたか』他。




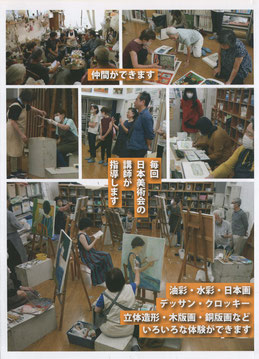
コメントをお書きください